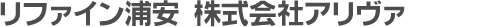「大工道具紹介」~トリマー~
トリマーは動物の美容師さん。
犬や猫などのカット、シャンプー、爪切りを行い、身だしなみを整える
仕事を言います。
・・・というのが私が一番最初に思いつくトリマーなのですが、
大工道具としてのトリマーがあることを皆さんはご存じでしょうか?
大工道具「トリマー」は、回転軸に取り付けた
ビットといわれる刃物を超高速で回転し、
材料の角の面取りや溝堀などに使用する、
電動工具のことを言います。
以前にも紹介した、ノミやカンナでも溝を掘ったり
面取りをすることは可能ですが、均一に作業するには
長年の経験を積まないと難しい作業となります。
そんな面倒な作業も電動トリマーを使えば、楽々こなしてくれるのです。
また、刃物の使える種類は使用するトリマーにもよりますが、
基本的には溝堀用のビットと面取り用のビットがあります。
いくつも揃えておくと、飾り気のない木材に溝を掘ってデザインできるので、
オリジナル作品が作れること間違いなしです。
アイディアを思い浮かべ、
早速、ホームセンターに週末、向かってみてはいかがでしょうか。